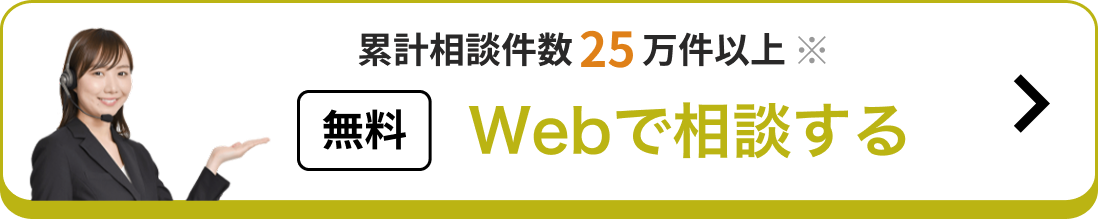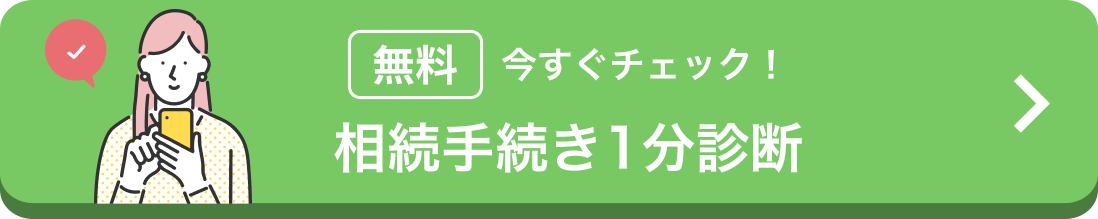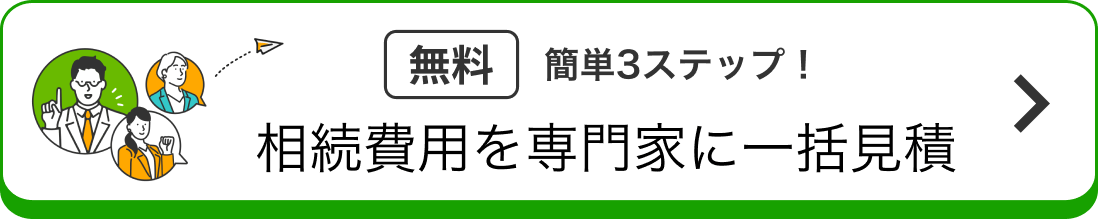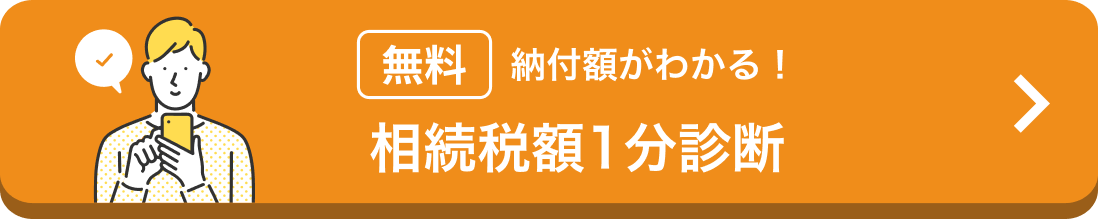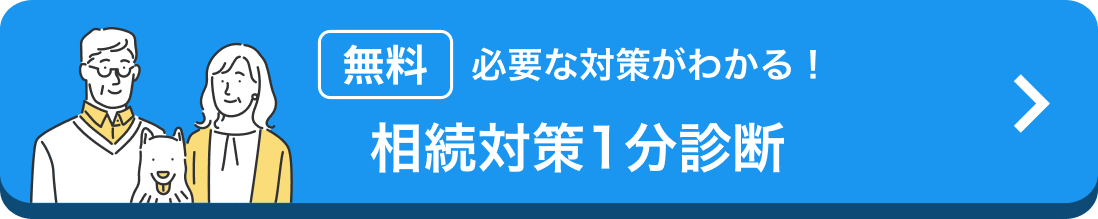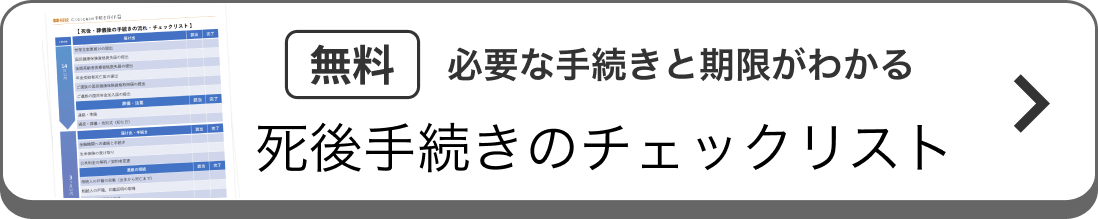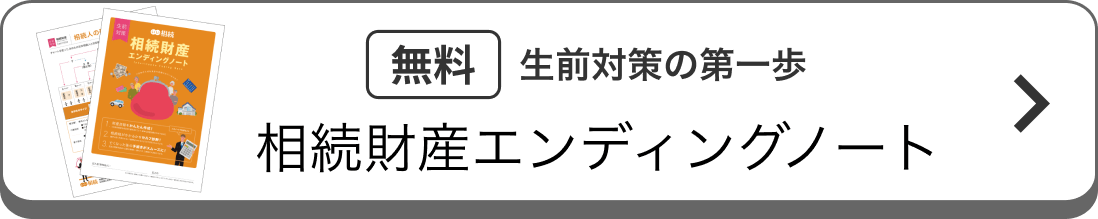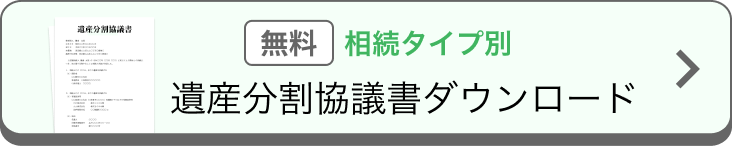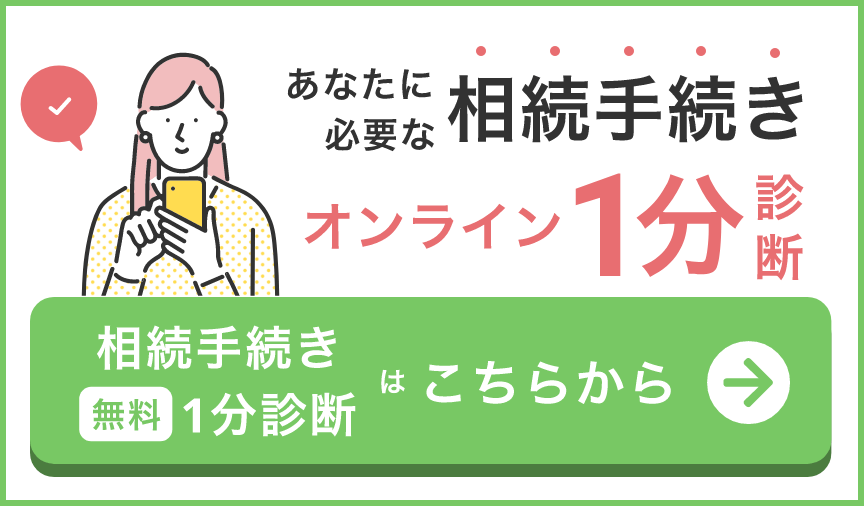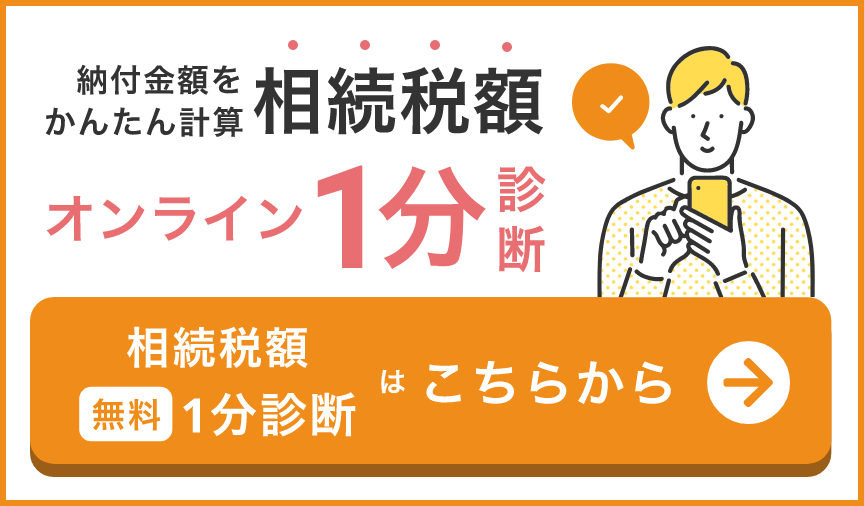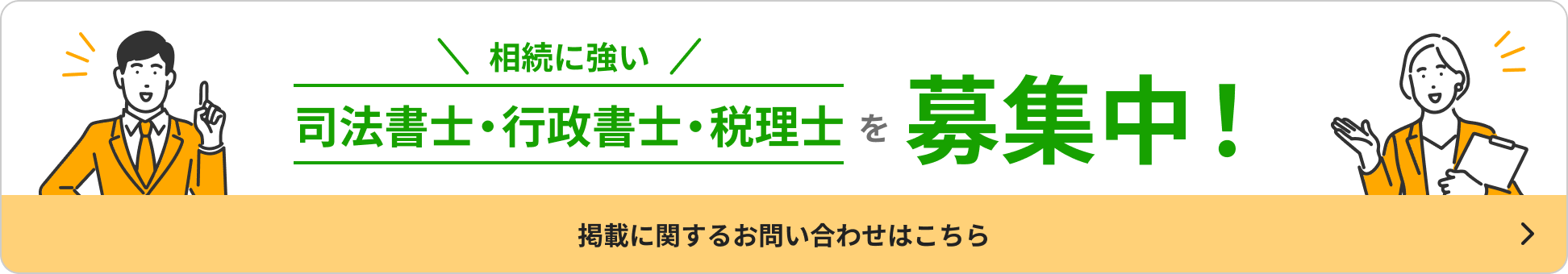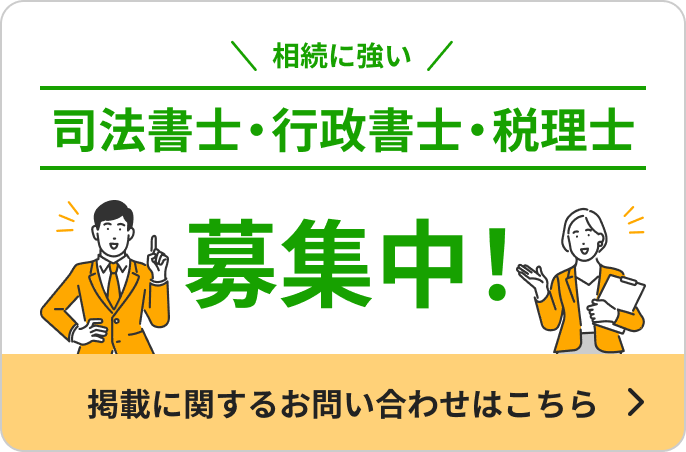期限なし、利子なしで親子間の借金をしてました。遺産分割に影響はある?
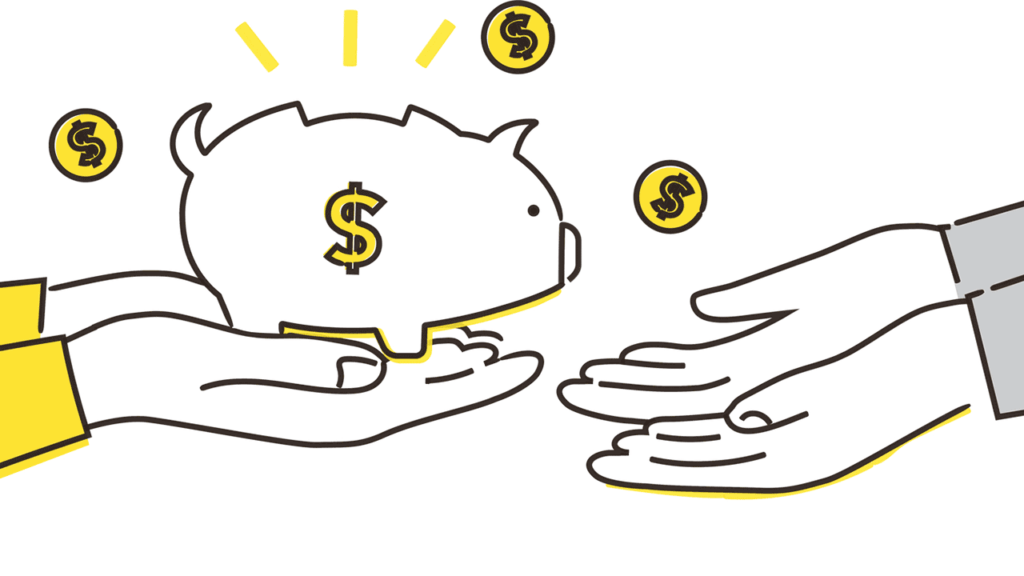


父から親子間ということで2000万円を期限なし、利子なしの借用書でお金を借りていました。まだこのお金を返していませんが遺産分割で影響を及ぼしますか?


税務上はその行為の「実態」を見る
税務上の考え方では、どんな金銭のやりとりに課税されるかは、あくまでも「形式」ではなく「実態」を見ることになっています。
よって、たとえ親子間で「貸し借り」の約束をしていたと言い張っても、期限も利子もないというのは一般的な金銭消費貸借(お金の貸し借り)ではありえないわけですから、それは実態として「贈与」であると認定されてしまいます。したがって、渡した金額に対して贈与税がかかってきます。
贈与税の申告期限は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。贈与を受けた人が申告する必要があります。
遺産分割協議に対する影響
子供がまったく返済していないとなると実質的には贈与となるため、遺産分割協議においてはこれを無視すれば不公平感が生じることがあります。
このとき「婚姻や養子縁組のため」「生計の資本としての贈与」については、「特別受益」といって、相続分を前渡ししたものとして扱います。
生計の資本の具体例としては、「住宅資金」「開業資金」などの費用に充てたものがあります。
前渡しとされた相続分は、いったん相続財産に「持ち戻し」をしてから各相続人に配分することとなります。 では、実際の計算を見てみましょう。
▶遺産分割について|遺産分割のための手続きと注意点。トラブルを防ぐためのポイント特別受益がある場合の相続分の計算
特別受益がある場合は次の方法で計算します。
たとえば父親が死亡、母はすでに他界し、兄弟3人が相続人である場合で、父死亡時点で存在した相続財産が4000万円あり、兄弟の一人が2000万円の生前贈与を受けていたとします。
(相続時に存在した財産)4000万円+(生前贈与分の財産)2000万円=6000万円
各人の法定相続分(民法で定められた相続分)は3分の1ずつとなるため、
6000万円/3=2000万円これが各相続人の法定相続分ですが、生前贈与を受けた相続人については
(法定相続分)2000万円-(生前贈与=特別受益)2000万円=0 となります。
ただし、もし生前贈与を行う場合でも贈与する人が相続分とは無関係に行いたいと思っているのであれば、遺言でその旨を意思表示しておけば持ち戻しを行わずに遺産分割させることもできます。
このような取り扱いにする場合は、あくまでも他の相続人の「遺留分」を侵害しないようにしなくてはなりません。遺留分とは被相続人(相続される人=財産を残す人)の配偶者や子など一定の範囲の相続人に法律上必ず保障された相続財産の一定割合です。
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。