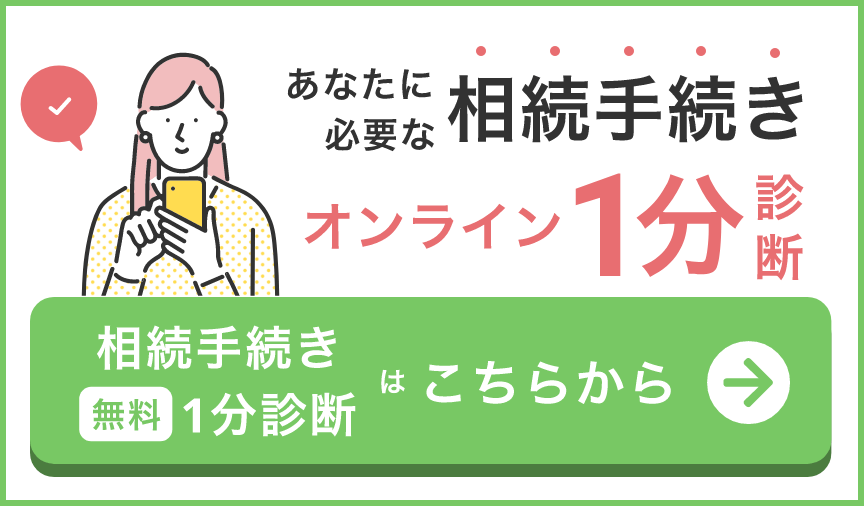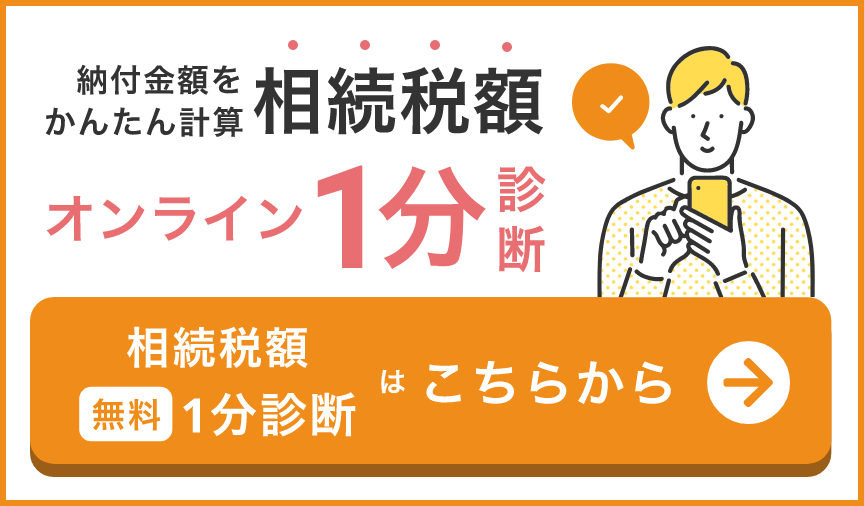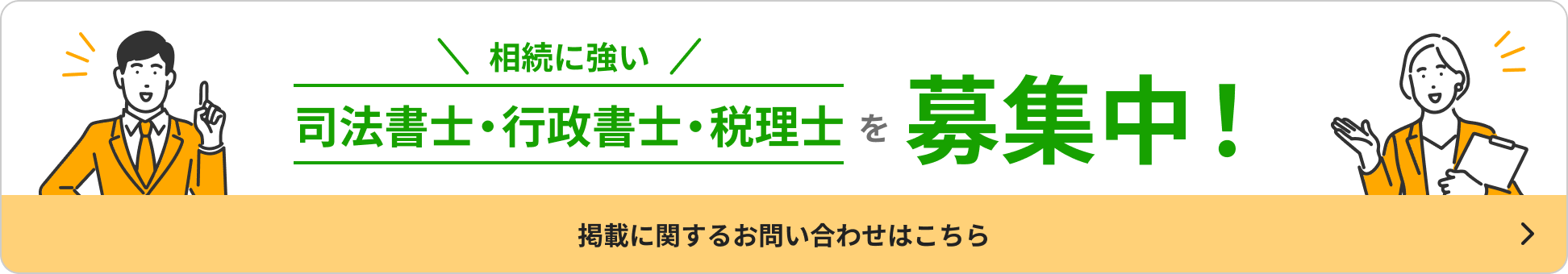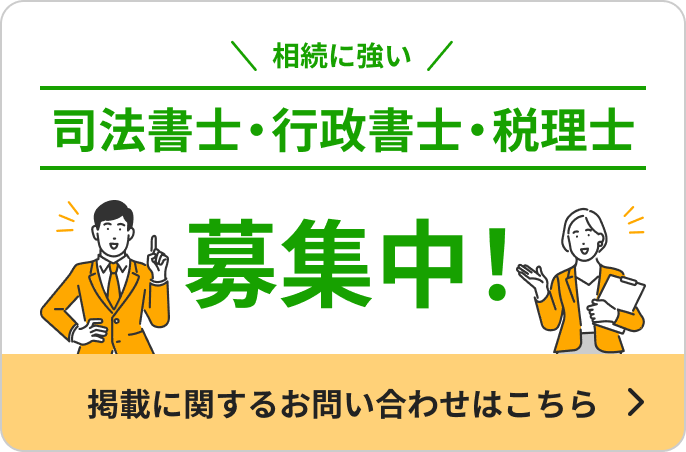遺留分とは?遺言や贈与で取られた相続財産を取り戻す方法を解説

最近では、節税を目的として生前贈与に注目が集まっています。さらに、相続でもめないよう遺言書を作成しておくことも推奨されています。
しかし、実際に、自分が生前贈与や遺言で不公平な扱いを受けたら、納得いかない人も多いのではないでしょうか?
そこで、遺言や贈与で持っていかれた相続財産を取り戻す方法として、遺留分という制度について解説します。
遺留分とは?
遺留分とは、被相続人(相続される人=財産を残す人)の配偶者や子など一定の範囲の相続人に法律上必ず保障された相続財産の一定割合です。
相続人となる人や各相続人の相続分については民法に定められていますが、遺言や生前贈与、死因贈与によって相続財産が減ったり無くなったりすることがあります。
被相続人と近しい関係の本来の相続人が、まったく遺産を取得できなくならないよう、民法では、一定の範囲の相続人に対して、法定相続分の一定割合を遺留分として請求できるようにしているのです。
▼忘れている相続手続きはありませんか?▼

遺留分を請求できる人

遺留分を請求できるのは、被相続人との関係が次の4つのいずれかに該当する人です。
- 配偶者
- 子
- 子の代襲相続人
- 直系尊属
このうち、配偶者、子、子の代襲相続人については、原則として遺留分が認められますが、直系尊属に遺留分が認められるのは、子や子の代襲相続人がいない場合です。
配偶者
妻や夫のことです。婚姻届を提出していない内縁関係は配偶者とはみなされません。
子
養子も実子と同様に遺留分をもちます。
実親と養子に出された実子の関係については、養子縁組の種類によって取り扱いが異なります。
普通養子縁組の場合、養子は養親のみならず、実親の相続についても遺留分があります。特別養子縁組の場合の養子は養親の遺留分はありますが、実親に関しては遺留分をもちません。
子の代襲相続人
代襲相続とは祖父母よりも先に親が亡くなったような場合に、祖父母の遺産を孫が相続できる制度です。子の代襲相続人は、被相続人との関係でいう孫に当たります。
直系尊属
直系尊属とは、親や祖父母等のことです。
直系尊属に遺留分が認められるのは、前述の通り、子や子の代襲相続人がいない場合に限ります。
子や子の代襲相続人がいない場合は、まず親が対象となり、親もいない場合は祖父母が、祖父母もいない場合は曽祖父母が対象となります。
▼まずはお電話で相続の相談をしてみませんか?▼遺留分を主張できるとき
遺留分を主張できるのは、自己の最低限の取り分を侵害されていたときです。自己の最低限の取り分が侵害されるという事態は、被相続人による次の行為によって起こります。
- 生前贈与
- 死因贈与
- 遺贈
生前贈与
生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を贈与することです。「贈与」とは、贈与契約のことで、贈与者と受贈者の合意によって成立します。
死因贈与
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効果が生じる贈与契約のことです。贈与契約は生前に行われていますが、実際に贈与を受けることができるのは、贈与者の死亡時です。
遺贈
遺贈とは、遺言によって、無償で自分の財産を他人に与える処分行為のことです。遺贈を受ける人のことを「受遺者」といいます。
▼今すぐ診断してみましょう▼遺留分の計算方法
遺留分の割合
遺留分割合は、基本的には法定相続分の2分の1ですが、直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1になります。
例えば、配偶者と子1人が法定相続人の場合、それぞれの法定相続分は2分の1ずつとなり、遺留分は、法定相続分の2分の1のため、相続財産の4分の1ずつとなります。
父母が法定相続人の場合は、父母の法定相続分はそれぞれ2分の1ずつとなり、このケースでは遺留分は法定相続分の3分の1ですから、遺留分は相続財産の6分の1ずつとなります。
遺留分のための生前贈与の持ち戻しの計算方法
生前贈与があった場合、下記に当たる生前贈与だけが遺留分を侵害していると判断され、持ち戻すことができます。
- 相続開始前1年以内に相続人以外に行われた生前贈与
- 被相続人の死亡より1年以上前の生前贈与のなかで、特別受益にあたる贈与(婚姻、養子縁組のための贈与、生計の資本のための贈与)のうち、一定の条件をみたす場合
- 被相続人の死亡より1年以上前の特別受益にはあたらない生前贈与のうち、贈与者と受贈者の双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知りながら行った生前贈与
なお、「遺留分権利者に損害を与える」と知っていたかどうかは、贈与当時の親の財産の状況などから判断されます。


遺留分を主張する方法
遺留分を主張する方法について説明します。
遺留分を主張できる期間
贈与や遺言によって、遺留分を侵害されていた場合には、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったとき」から1年以内に意思表示を行う必要があります。
つまり、遺留分を侵害する遺言の存在、贈与の存在を知ったときから1年以内に、遺留分侵害の意思表示をする必要があるということです。
なお、遺留分を侵害する贈与や遺言の存在を知らないままでも、相続開始から10年経つと、遺留分侵害額請求権を行使することはできなくなります。
遺留分侵害額請求の方法
1年以内に遺留分侵害額請求をしたかどうかは、非常に重要なことなので、証拠を残すために内容証明郵便(配達証明付き)によって行うべきです。
1年以内に遺留分侵害額請求をしておけば、遺留分侵害の調停や訴訟を行うのは、1年以内でなくてもかまいません。
ただし、この遺留分侵害の意思表示によって生じた法律関係に基づく目的物返還請求権にはさらに、その返還請求権の性質によって個々の時効があることもありますので、注意しましょう。
▼めんどうな相続手続きは専門家に依頼しましょう▼遺留分侵害額請求すると財産はどうやって返還される?
遺留分権利者が侵害額請求すると、請求された人は、遺贈や贈与で取得した財産の遺留分に相当する分の財産を返還しなければなりません。
ただし、遺留分権利者は返還される財産を選択することはでません。
基本的には、それぞれの財産に対して、遺留分に応じた持分を取得することになります。
例えば、遺留分が4分の1で、財産が現金1000万円と不動産であった場合は、現金250万円と不動産の4分の1の共有持分を取得することになります。
ただし、請求された人には価額弁償の抗弁権があり、上記のように現物を返還するのではなく、お金で清算することを提案することができます。
例えば、先ほどの例で、不動産の価格が7000万円であったとすると、現金1000万円と併せて、遺留分算定の基礎となる財産の価額は8000万円になり、遺留分が4分の1であれば、2000万円を弁償することで、現物の返還に代えることができます。
価額弁償の抗弁がなされていないのに、遺留分権利者の方から価額弁償を求めることはできません。
なお、価額弁償の抗弁があったにもかかわらず、弁償されない場合は、遺留分権利者は、価額弁償の請求前であれば現物の返還を求めることができます。
一度でも価額弁償を請求したら、翻意して現物の返還を求めることはできません(請求された人が同意すれば可能)。
価額弁償の抗弁があったが弁償されないという場合に、弁償を請求するかどうか、慎重に判断しましょう。
なかなか弁償されない場合、相手方に弁償を行うだけの資力がない可能性が高いので、現物の返還を求めたほうが取りっぱぐれるリスクが比較的低いと考えられます。
また、請求された人は、一部の財産についてのみ価額弁償を選択することもできます。なお、当事者同士の合意があれば、どのようなかたちで分割しても構いません。
例えば、対象の不動産が複数あり、その内の一つを遺留分権利者が取得するかたちや、分割払いで支払うかたちでも、当事者の合意があれば構いません。
ただし、その場合には、当事者で合意した分割方法によって税金面で不利な取り扱いを受けないかに注意が必要です。
▼あなたに必要な相続手続き、ポチポチ選択するだけで診断できます!▼遺留分の放棄
遺留分を放棄することは、その相続人にとって基本的にメリットはありません。しかし、他の相続人や、思い通りに財産を継承させたい被相続人にとってはメリットがあります。
また、放棄する相続人にとっても、代わりに生前贈与を受けられるといった交換条件があれば、メリットがある場合もあるでしょう。
以下では、遺留分の放棄について、被相続人の生前と、被相続人が亡くなった後に分けて説明します。
生前の遺留分放棄
遺留分の放棄
被相続人の生前に相続を放棄することはできませんが、遺留分は放棄することができます。遺留分の放棄とは、生前贈与や遺言によって自己の最低の取り分を侵害されても、相続開始後に遺留分侵害額請求を行うことができなくなるということです。
生前の遺留分放棄の方法
被相続人の生前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所で「遺留分放棄の許可」を受けなければいけません。遺留分放棄の申立は、被相続人となるべき人の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
家庭裁判所は、遺留分を放棄するという意思が、本当にその人の自由な意思であって、強要されたものではないかどうかを確認します。
それだけではなく、当事者間の具体的な事情から、放棄をしたいという理由の客観的な合理性、代償性などを判断して、許可をするかどうかを決めます。
代償性とは、遺留分を放棄する代わりに生前贈与を受けているなど、遺留分を放棄する対価を受けているかどうかことです。すでに対価を受けていれば、遺留分を放棄することも合理的であるとみなされます。
家庭裁判所が許可をすれば、遺留分を生前放棄したということになります。
生前の遺留分放棄の効果
・他の相続人の遺留分は増加しない
相続放棄をすると、他の相続人の相続分が増えます。しかし、相続人の1人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分が増加することはありません。
・相続人であることに変わりはない
遺留分を放棄しても、相続を放棄したわけではないので、「相続人」の資格は失いません。
そのため、例えば、被相続人が、遺言や贈与を行うことなく死亡した場合には、相続人は、法定相続分に従って、遺産分割をします。このときには、遺留分侵害額請求を行う必要はないので、遺留分を放棄した人も、本来の法定相続分をもって、遺産分割に参加できます。
また、「相続人」としての資格を失わないということは、相続債務(借金)があった場合には、借金を法定相続分の割合で相続するということです。借金を相続したくない場合には、相続開始後に相続放棄をする必要があります。
・家庭裁判所は、遺留分の放棄許可を取り消すことができる
家庭裁判所が遺留分放棄の許可の審判をした後、年月の経過等により、申立の前提となった事情が変化し、遺留分の放棄を許可しておくことが、客観的にみて不合理となった場合には、遺留分放棄の許可を受けていても、放棄許可の取り消しを家庭裁判所に申し立てることができます。
家庭裁判所がその申立に理由があると認めれば、遺留分の放棄許可の審判を取り消したり、変更したりすることができます。
また、相続が開始した後に、生前に行われた遺留分放棄の許可を取り消すこともできます。
相続開始後の遺留分の放棄
遺留分を侵害する贈与や遺言の存在を知ったときから、1年以内に遺留分侵害額請求をしなければ、遺留分を放棄したとみなされることになります。
相続開始後は、遺留分を放棄するための特別な手続きはありません。
▼相続手続きは一人で悩まず専門家に相談しましょう▼この記事のポイントとまとめ
以上、遺留分について解説しました。最後にこの記事のポイントをまとめます。
- 遺留分とは相続人に認められる最低限の遺産の最低限の取得割合
- 遺留分侵害額請求によって遺留分を取り戻すことも可能
- 被相続人が生きている間に家庭裁判所で「遺留分放棄の許可」を受けることも可能
遺留分を侵害された場合や、相続について問題があるときには、専門家への相談も検討してください。
いい相続ではお近くの専門家との無料相談をご案内することが可能ですので、遺言書や遺産分割でお困りの方はお気軽にご相談ください。


▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きや遺言書の作成を依頼した方のインタビューはこちら
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。





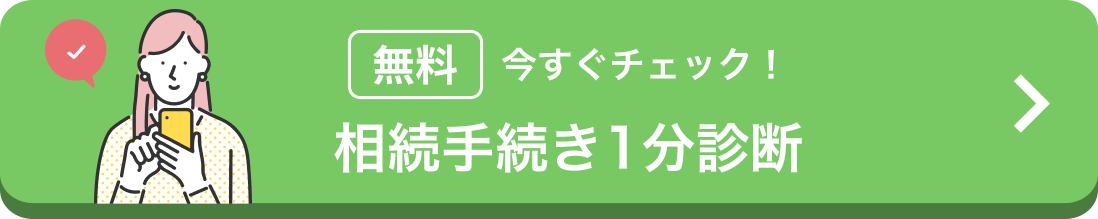
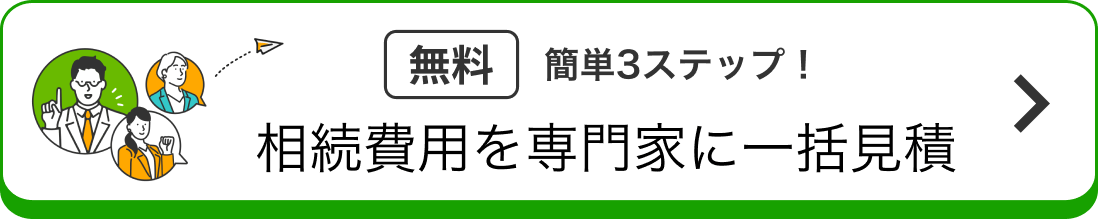
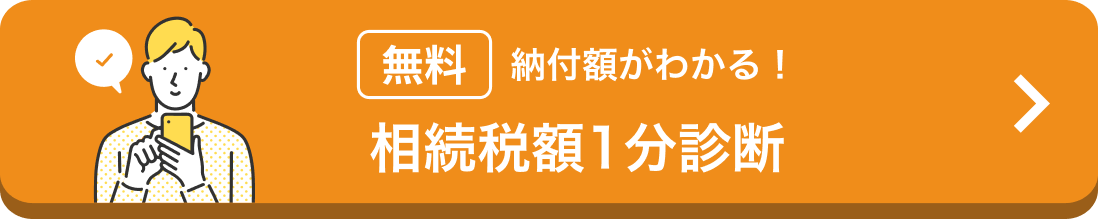
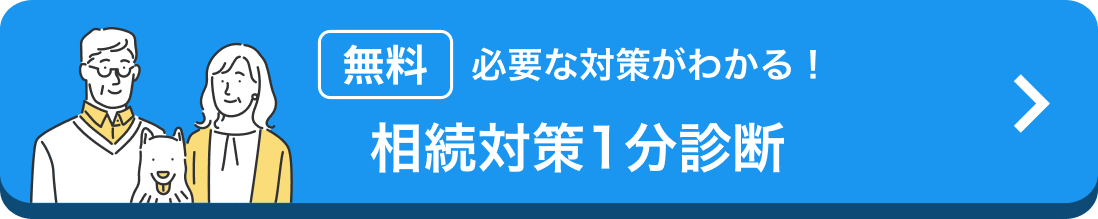
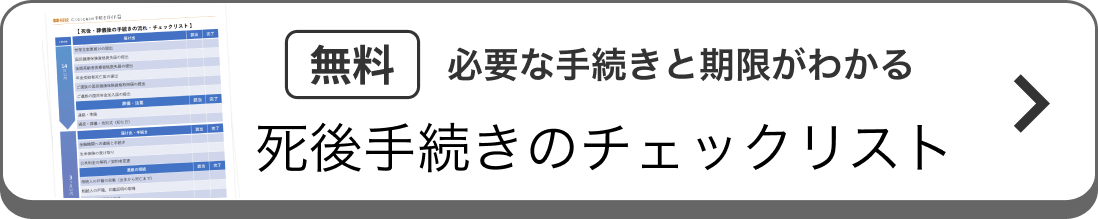
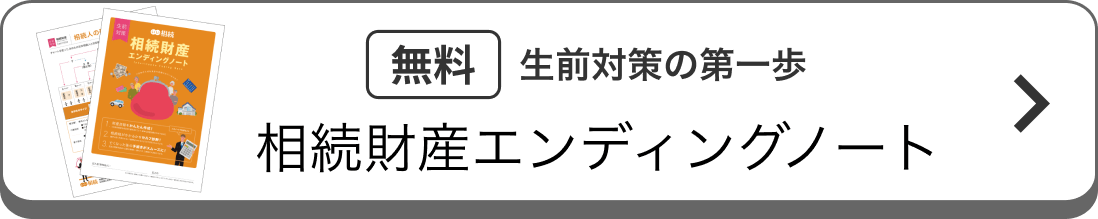
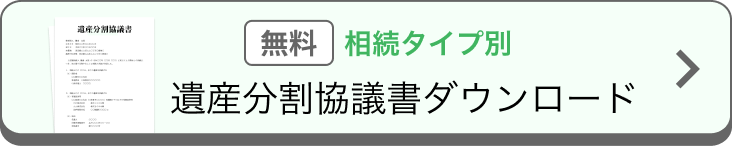

 Webで無料相談はこちら
Webで無料相談はこちら