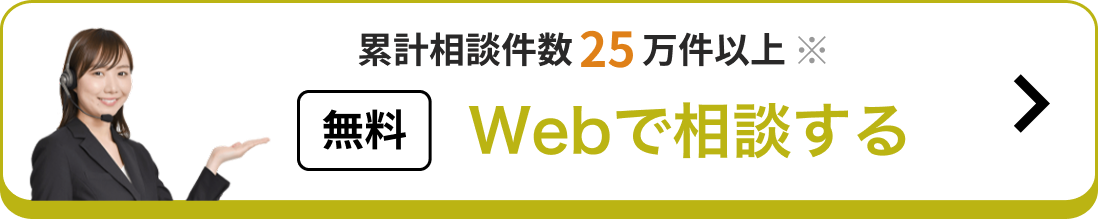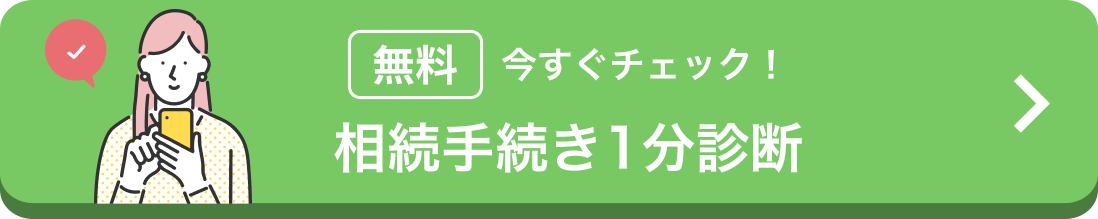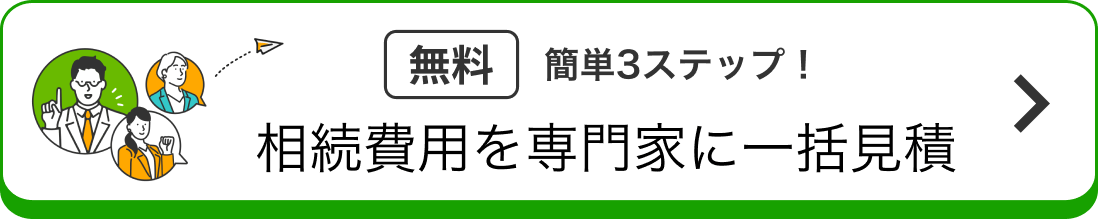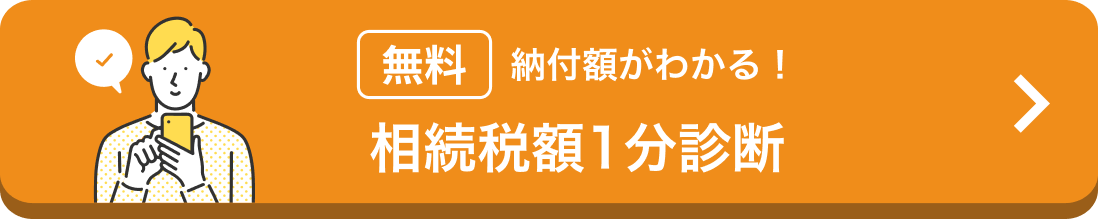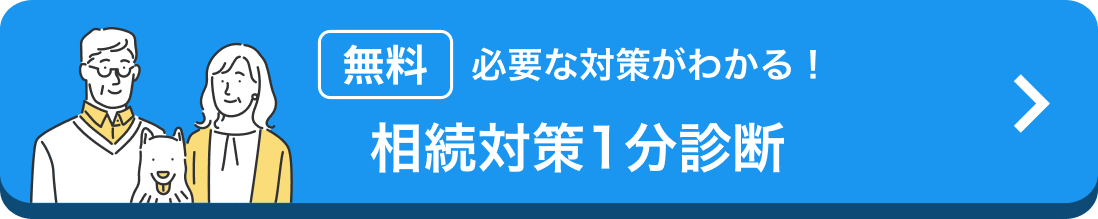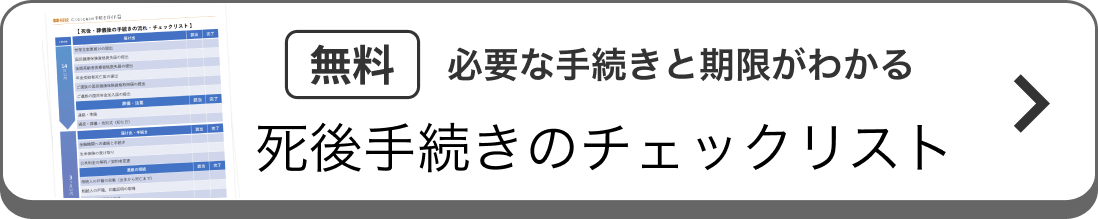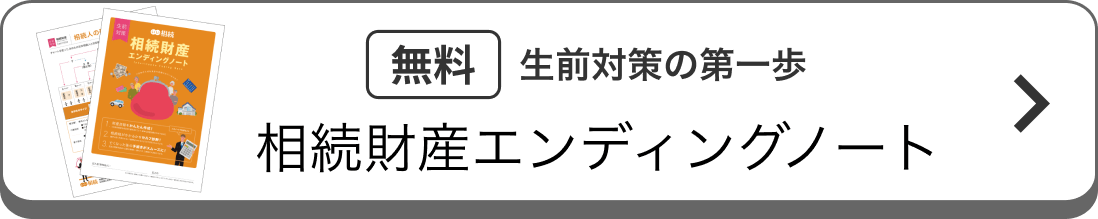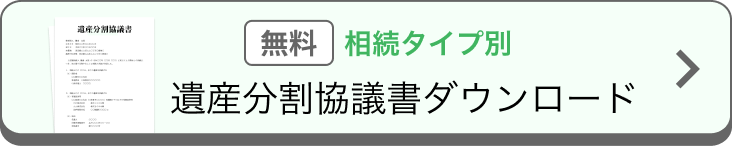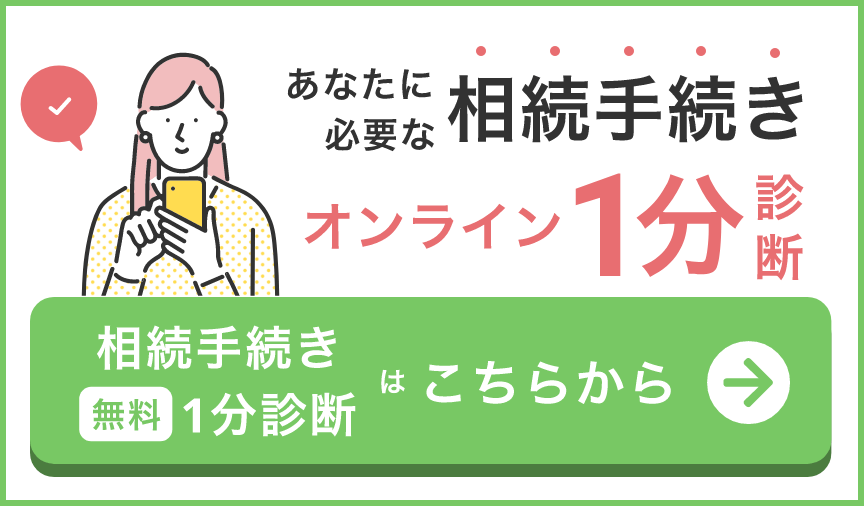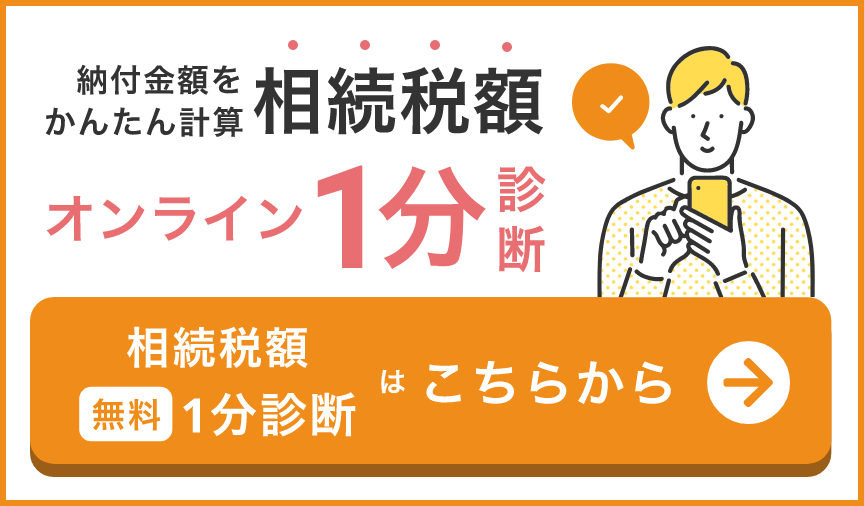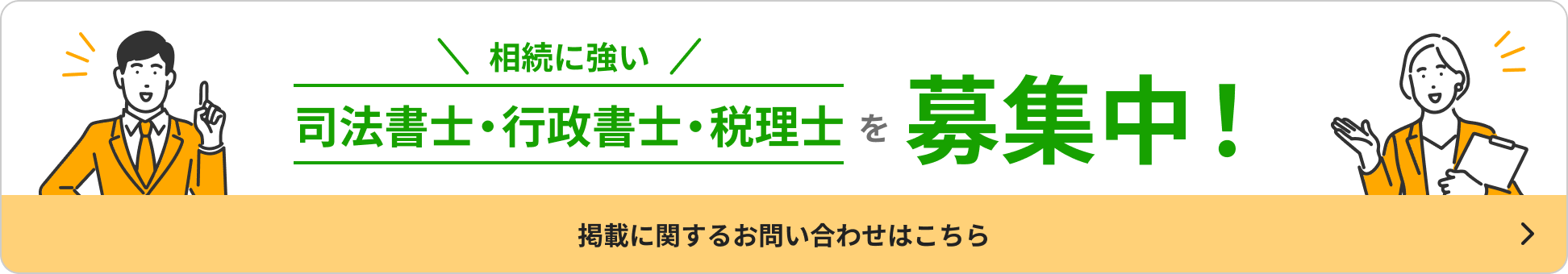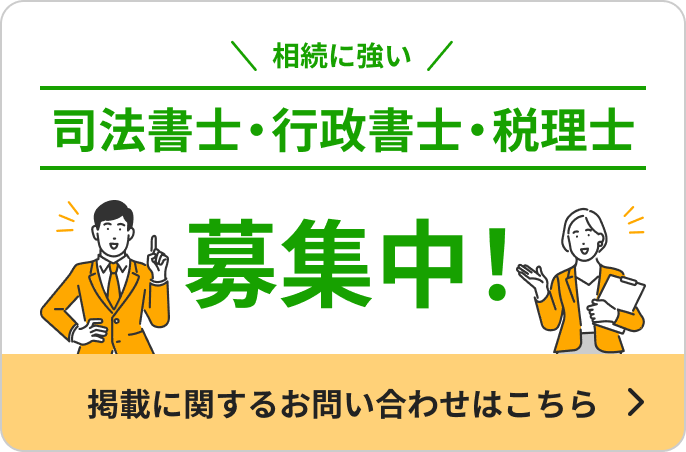【よくある質問】私が亡くなった後に子供たちが喧嘩になりそうなので遺言でそれぞれの相続財産を決めておきたいと思います。遺言で財産を残すポイントを教えてください。



私が亡くなった後に子供たちが喧嘩になりそうなので遺言でそれぞれの相続財産を決めておきたいと思います。遺言で財産を残すポイントを教えてください。
遺言書を残すことは、自分の死後、無用なトラブルを防ぐため必須です。ただ、やみくもに書けばいいというものではなく、必ず押さえておきたいポイントがあります。
確実な遺言にするためには公正証書遺言で
遺言書のスタイルには主に使われるものとして「自筆証書遺言」「公正証書遺言」があります。前者は自分で便箋などを準備して自書するスタイル、後者は公証役場に行って作成し、公証人のお墨付きをもらうスタイルです。 被相続人(亡くなった人)の死後、遺言書の効力が争いになることもしばしばありますが、少なくとも公正証書遺言にしておけば公証人と証人2名の前で作成するわけですから「遺言者が自らの意思で遺言書を作成した」ことだけは確実になります。
また、不動産などの特定で「自筆証書遺言」の場合は曖昧になってしまうことも多いのですが、こういった点も公証役場を通せば明確な記載にすることができます。 さらに、実質的に公正証書遺言は公証役場に永久保存となりますので、改ざんなどされる危険がありません。つまり、遺言書の存在さえきちんと周囲の人(なるべく自分よりかなり若い人)に伝えておけば自分の遺志を実現することができるのです。
▶公正証書遺言の作成方法/流れ・費用・必要書類と遺言書の種類別一覧
「遺留分」への配慮が必須
遺言書を書く際のコツとしては、「遺産の配分は自由であるが、必ず遺留分に配慮することを忘れない」ということです。 遺留分というのは、遺族の生活に配慮して「最低限これだけは取り分を保証する」とされている各相続人の権利のことです。
兄弟姉妹以外の者が相続人になる際には必ず遺留分があり、基本的には各人の法定相続分の2分の1、直系尊属(親、祖父母)のみが相続人になる場合には法定相続分の3分の1となっています。 昔であれば「財産は長男が相続するのが当たり前」などと思われていたでしょうが、現代では各相続人の個人としての権利意識が強まっているため、ことさら注意が必要です。
▶遺言書と遺留分どちらが優先|相続で揉めないための遺留分についての全知識
「付言」で遺言書に説得力を持たせる
遺言書を読んだ際の相続人のイメージを大きく左右するのが遺言書の最後に任意で記載する「付言」の記載内容です。 付言は、被相続人が自由に自分の思いを記してかまいませんが、ここにぜひ書いておきたいことは「各相続人への感謝の気持ち」と「財産をなぜそのように配分したかの理由」です。 特に、財産に差をつけた場合は何の理由も書かれていないと納得がいかない相続人は必ず出てきます。 よって、そこに相続人の気持ちに配慮した一言があるだけでも、自分亡き後の子供たちの争いを防ぐことができる要因となるのです。
▶遺言書の種類と書き方、その効力。種類別作成方法と注意点【行政書士監修】
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。