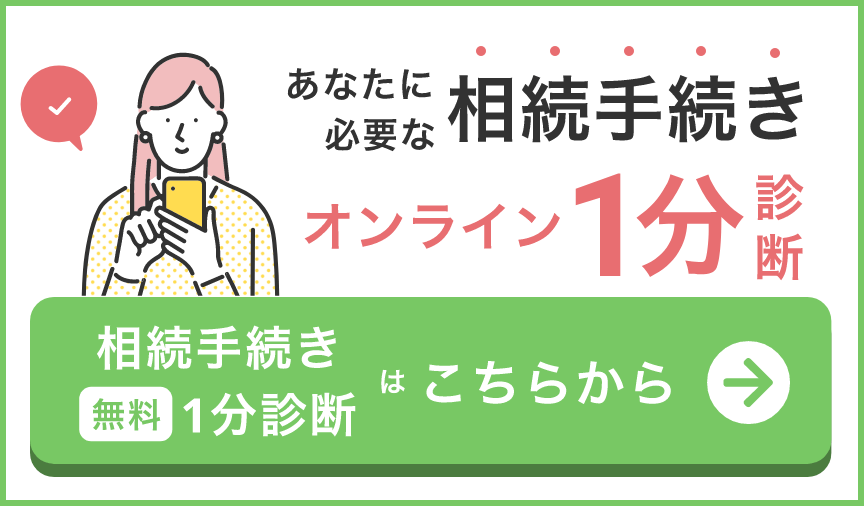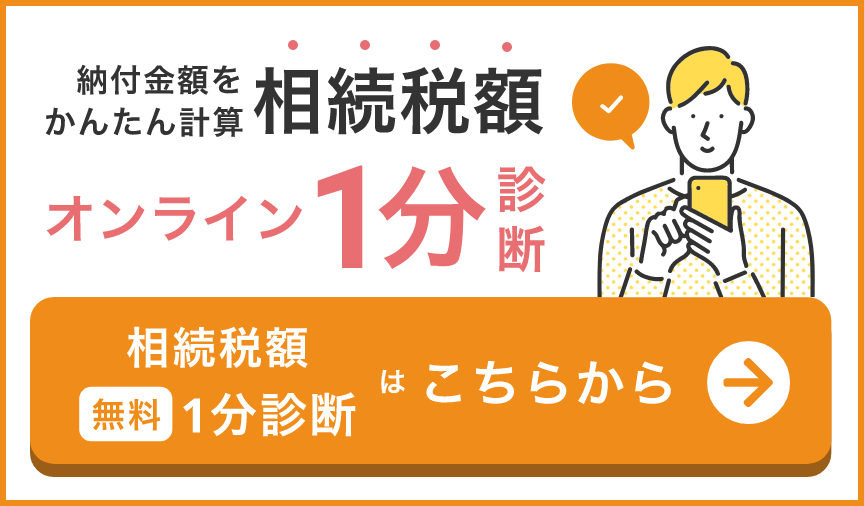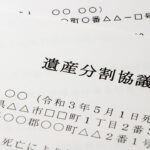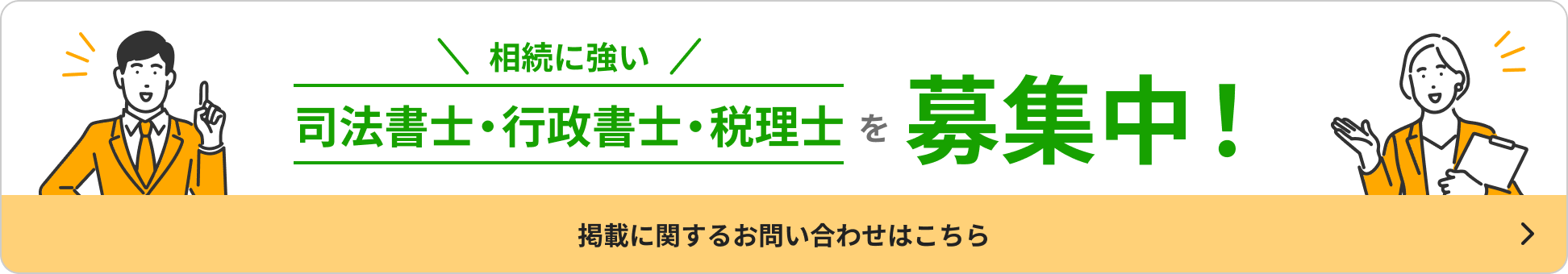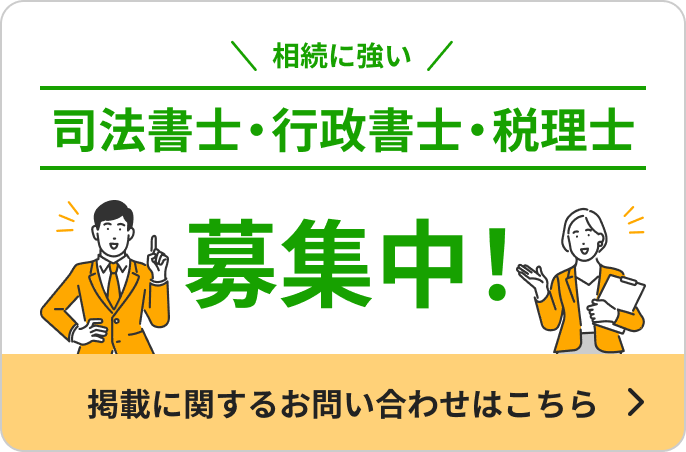【不動産取得税】相続の場合は非課税で申告も不要!登録免許税はかかる

不動産を取得した場合に、不動産取得税という税金がかかるという話を聞いたことがある人が多いと思います。
それでは、相続で不動産を取得した場合にも、不動産取得税はかかるのでしょうか?


相続の場合は不動産取得税は非課税
結論から言ってしまうと、相続した不動産については、不動産取得税は非課税で、不動産取得税に関しては申告も不要です。
相続以外で不動産取得税が非課税になる場合
相続以外にも、包括遺贈や、相続人に対してなされた特定遺贈の場合には、不動産取得税はかかりません。
遺贈とは、遺言者が死後に財産を人に無償で譲与することです。遺贈は、相続人以外の人に対してすることもできます。
包括遺贈とは、財産の全部又は一部を包括的に遺贈するもので、財産に対する一定の割合を示してする遺贈をいいます。
例えば、「全財産の3分の2を○○に、3分の1を××に遺贈する。」というような遺贈が包括遺贈です。
この場合、割合的な一部を受け取った受遺者(遺贈を受ける人)の中で遺産分割を行うことになります。
特定遺贈とは、特定の物や権利、あるいは一定額の金銭を与えるというように、財産を特定してする遺贈(割合で示されていない遺贈)をいいます。
例えば、「○○県○○市○○町〇丁目〇番〇号の土地をAに遺贈する。」というような遺贈が特定遺贈です。
特定遺贈により取得した不動産の不動産取得税が非課税になるのは、特定遺贈が相続人に対してなされた場合に限ります。
相続人以外の人が特定遺贈により取得した不動産には、不動産取得税が課税されます。
▼相続手続きは一人で悩まず専門家に相談しましょう▼不動産取得税が課税される場合
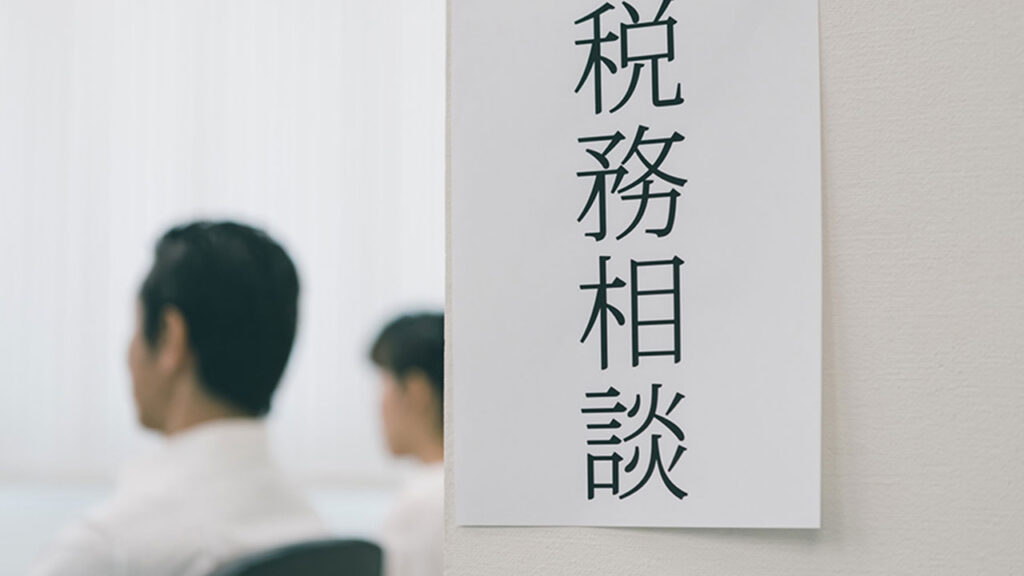
相続、包括遺贈、相続人に対してなされた特定遺贈の3つ以外の方法により取得した不動産には不動産取得税がかかります。
例えば、次のようなかたちで取得した場合には不動産取得税がかかります。
- 売買
- 新築
- 増改築
- 贈与(死因贈与を含む)
- 交換
- 相続人以外に対してなされた特定遺贈
なお、贈与によって取得した不動産に対する課税方式として相続時精算課税を選択した場合でも、贈与によって取得しているので、不動産取得税がかかります。
▼何をすればいいか迷っているなら、今すぐ調べましょう▼

不動産取得税の税額の基本的な計算方法
不動産取得税の税額の基本的な計算方法は、「課税標準×4%」です。
しかし、2024年3月31日までに取得した土地と住宅については、税率が3%になります。
課税標準は、原則は、固定資産税評価額と同額ですが、2024年3月31日までに取得した宅地については、課税標準が「固定資産税評価額の2分の1」になります。
つまり、2024年3月31日までに取得した宅地の不動産取得税は、固定資産税評価額の1.5%になります。
固定資産税評価額は、市町村役場(東京23区は都税事務所)で管理している固定資産課税台帳に記載されています。
マンションの場合は、通常、敷地権が付いているので、区分建物(専有部分)にかかる税額と敷地権にかかる税額を合計します。
敷地権の固定資産税評価額は、敷地全体の固定資産税評価額に敷地権の割合(共有持分)を掛け算して計算します。
敷地権の割合も固定資産課税台帳に記載されています。
なお、マンションの敷地も、宅地なので、課税標準が固定資産税評価額の2分の1になります。
不動産取得税の税額軽減措置
また、不動産取得税には、様々な税額軽減措置があります。
税額軽減措置は、申告しなければ適用されません。
要件と申告方法については、課税対象不動産がある都道府県の税事務所にご確認ください。
申告期限は取得日から60日以内のケースが多いのですが、東京は30日以内、大阪は20日以内と、短いことがあります。
なお、軽減措置の適用を受けられるにもかかわらず申告せずに期限を過ぎてしまった場合は、都道府県の税事務所に相談するとよいでしょう。
多くのケースでは、期限を過ぎても軽減措置の適用を受けられます。
既に納付済みの場合でも、不動産の取得日から5年以内に申請すれば還付を受けることができるでしょう。
▼あなたに必要な相続手続き、ポチポチ選択するだけで診断できます!▼


相続の場合でも登録免許税はかかる
相続の場合でも、登録免許税はかかります。登録免許税は、登記の際にかかる税金です。
相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。
贈与や売買の場合は2%なので、登録免許税も相続の方が割安になっています。
登録免許税について詳しくは「登録免許税は不動産を名義変更する登記で払う税金!相続税、不動産取得税との違いも解説」をご参照ください。
▼依頼するか迷っているなら、まずはどんな手続きが必要か診断してみましょう▼

まとめ
以上、相続の場合は不動産取得税はかからないということ等について説明しました。
相続登記については司法書士に依頼するとよいでしょう。
相続に精通した司法書士であれば、登記を依頼することで、不動産取得税を含め、相続手続きについて不明な点を色々と相談できるでしょう。
司法書士報酬は司法書士によって異なるので、まずは、電話等で、報酬について問い合わせて比較してみるとよいでしょう。
▼まずはお電話で相続の相談をしてみませんか?▼
▼実際に「いい相続」を利用して、専門家に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。




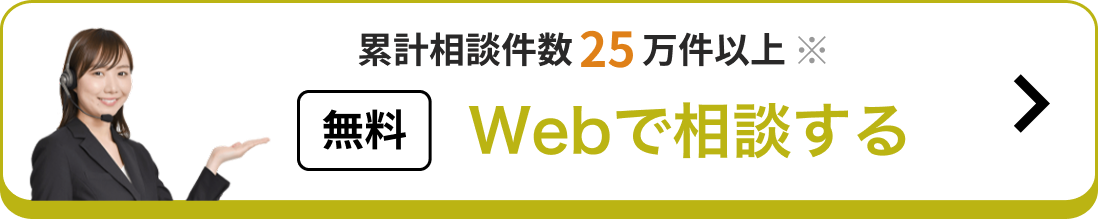
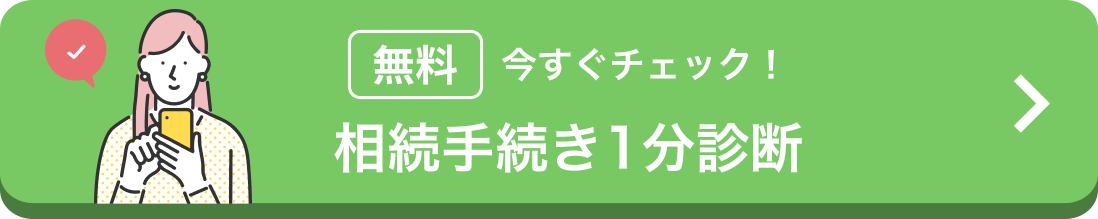
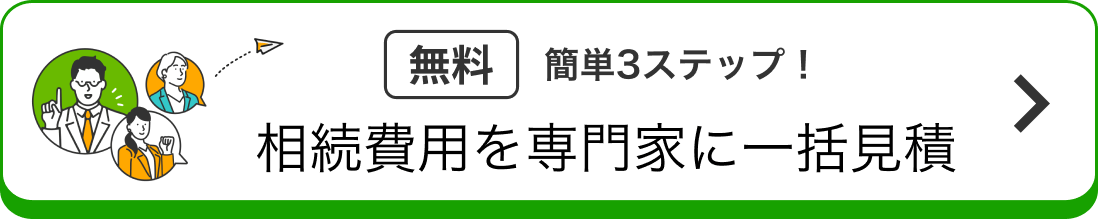
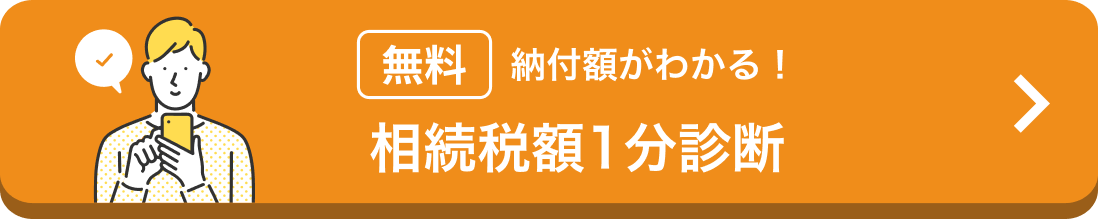
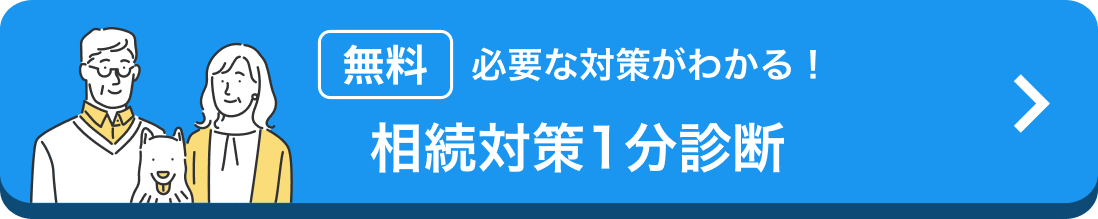
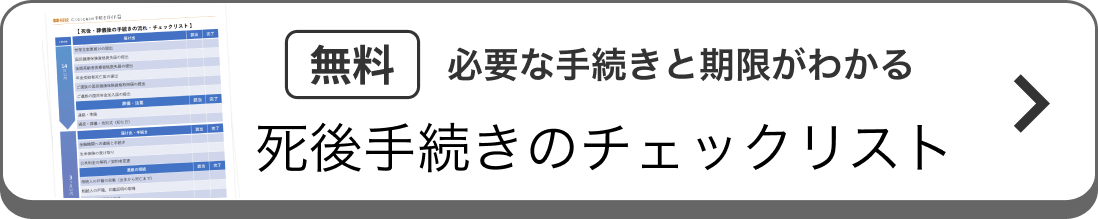
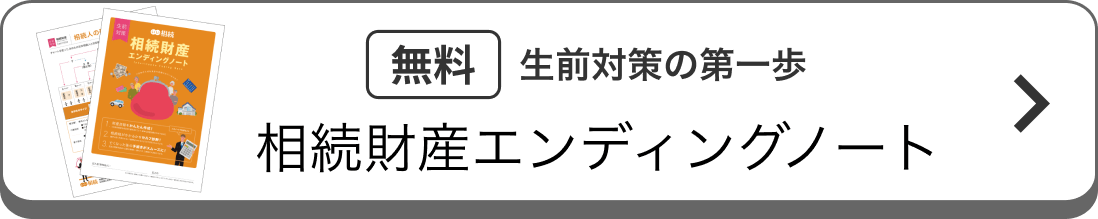
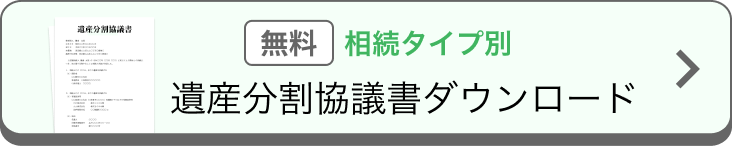
 Webで無料相談はこちら
Webで無料相談はこちら